「憲法制定という革命」
上村 剛さん(関西学院大学法学部准教授)
アメリカ革命という表現
『アメリカ革命』という新書を8月に上梓した。
この本、まずもってタイトルが異様にうつるらしい。異なる機会に、異なる人たちから、なぜこのタイトルか?という趣旨の質問を受けた。日本語でアメリカ建国を表す表現は、通常は独立、もしくは独立革命であって、単に革命と呼ぶのは珍しいようである。
なぜこのようなタイトルを付したか。最もシンプルな答えは、英語でAmerican Revolutionという表現が一般的だからそのまま日本語に取り入れた、というつまらないものである。とはいえ、それを超えて、筆者のアメリカ建国理解があらわれてもいる。その理解とは、合衆国連邦憲法の制定こそ、かの国が独立時に成し遂げた人類史上の貢献であり、それは革命と呼ぶにふさわしい、というものだ。
ここでいう合衆国連邦憲法とは、1787年の5月から9月にかけて、13の邦(憲法批准後は州)のうち12の代表が集まり(ロードアイランドは憲法制定に反対し欠席)、草案を作成し、そののちそれぞれの邦で批准会議を開催し、その批准をもって制定されたものである。国家の根本的なしくみをこのように特別な会議で多くの人たちが作成し、なおかつ別の会議で別の人々が投票で賛同を示す、という大がかりな過程は、稀有のことだったと言わねばなるまい。当然そのあいだには、憲法案をめぐって多くの論争がかわされた。そして、多くの智慧が集められた。
文字で書かれたかたちで、国家の根本的なしくみを、かくも多くの人が作る。これは法学的にもまさしく「革命」と呼ぶべき偉業である。単に英本国から独立した、というだけのお話にはとどまらないのである。イギリスとの関係だけでは、アメリカの革命が成し遂げた意味が、十全には理解できない。
なぜ憲法制定に「失敗」したアメリカが発展したのか?
しかもこの憲法が面白いのは、多くの人が集まって作ったがゆえに、制定当初は失敗作だとみなされていたことだ。成文憲法というしくみもユニークながら、それをとても多くの人数(会議参加者だけでも55人であり、かつ批准過程にかかわった人たち、意見を表明した人たちは少なくともその数十倍にのぼる)で作るというのもまた、ユニークだ。
一人の人間で作ったのではないから、体系的ではなく、一貫した政治思想の制度化にもならない。矛盾した箇所もあれば、規定をうまく作れずに抜け落ちていたところもあった。しかも憲法制定会議の結果、内乱が起きるのではないかとある参加者がおそれたくらいに、邦同士の対立は激化した。
このようなかたちで制定された、つまりは失敗作のようにみえる憲法をもつアメリカ合衆国は、なぜその後、覇権国家への道を歩んだのか。これが筆者の抱く、アメリカ革命への素朴な疑問である。一貫した説明はなお今後の研究を待たねばならないが、一つの鍵は、最初から対立が国家原理にビルトインされていた、というところにあるのではないかとにらんでいる。
対立の政治思想
人間が異なる存在である以上、お互いに対立するのは、本性上仕方がないことである。とすれば問題は、それをどうポジティブな力に転化するか。このように考える、対立の政治思想史とでも呼ぶべきものがある。人間は野望を持つ生き物であるから、たとえ嫌であっても、野望を無くすのは不可能である。とすれば、野望には野望をもって対抗させねばならない―『フェデラリスト』という連邦憲法についての古典(1787-88年)でそう説いたジェイムズ・マディソンは、具体的には抑制均衡という新たな政治思想でもって、対立の制度化に貢献した。
このように対立を組み込んだ連邦憲法が作られて、アメリカ合衆国は始まった。建国直後、連邦憲法をめぐっては解釈も安定せず、しばしば政治対立を呼び込んだ。だがそのような連邦憲法は、外国とのさまざまな軋轢と国際的な対立に翻弄されるなかで、1790年代以降聖典と化し、その内容は国家原理となった。国家原理がまとまったかたちで文字化されていると、建国者以降の世代も、その国家原理を把握しやすい。連邦国家の始まりが、事細かに確認できる。そして、常に立ち返るべき原点となる。こうして、連邦憲法という一つの柱が、連邦国家の拡大に大きな役割を果たした。
現代日本の参照軸としてのアメリカ合衆国連邦憲法
それから240年近くが経過した。連邦憲法は、いまなお超大国の国家原理である。現在でも、修正条項や法解釈の変更こそあれ、1787年に制定された連邦憲法は存続し、運用されている。彼らの国家原理を理解するうえで、建国者たちの政治思想はよく参照される基軸である。
他方、分極化というかたちで、対立が、ときに血を流すかたちで激しくなっている。アメリカの分極化は、感情的なものをふくめて極端な例かもしれない。だが、党派対立、分断といったテーマについては日本でもさまざまな意見がかわされている。分断を招くとして争いを押し鎮めようとする態度もあれば、もっと分断を、対立を、と煽る声もある。
そこで大事になるのは、党派や対立(や合意形成や妥協)をめぐる政治思想がどのように歴史的に検討されてきたのかを振り返ることである。西洋政治思想史の系譜のなかでは、党派対立という概念は定義もさまざまに下されてきたし、相対的によい党派と悪い党派の区別も論じられてきた。政党という私たちに馴染みのあるしくみも、そこから登場した。三権分立もそうだが、個人と個人の対立といった道徳的な問題ではなく、統治機構に組み込む工夫もみられてきた。このような、長い歴史的文脈のなかに現在の政治を位置付けてこそ、対立をめぐる問題は理解可能になるのではないか。このように考えるのが、憲法や統治機構について考える政治思想史の思考の癖である。アメリカ合衆国の連邦憲法は、その思考を映し出す鏡である。
このように、アメリカ革命を理解しようと試みることは、単にアメリカ合衆国の過去を理解するだけにとどまらない意味を持つ。それは、日本国憲法について考える際にも同様である。成文憲法の歴史において、アメリカの憲法は始まりだからだ。アメリカ革命が作り上げた合衆国連邦憲法は、今日の政治的なイシューたる日本国憲法について考える際にも、確固たる参照軸としての輝きを放っているのである。
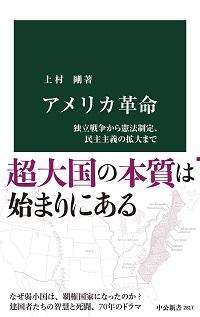

◆上村 剛(かみむら つよし)さんのプロフィール
関西学院大学法学部准教授。1988年東京都生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。著書『アメリカ革命』(中公新書、2024年)、『権力分立論の誕生―ブリテン帝国の『法の精神』受容』(岩波書店、2021年サントリー学芸賞〔思想・歴史部門〕)。共編著『歴史を書くとはどういうことか―初期近代ヨーロッパの歴史叙述』(勁草書房、2023年)。共著『戦後日本の学知と想像力』(吉田書店、2022年)ほか。
