書籍『君たちの日本国憲法』
S.K
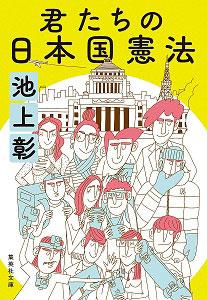
2021年の衆院選で、憲法改正を主張する政党が躍進し、衆議院の議席の4分の3を超えたことから、憲法改正の動きが活発になっています。しかし、立憲主義や民主的政治過程への無力感からか、そもそも憲法に従った政治への期待が薄いのか、多くの国民の憲法や憲法改正に関する意識に大きな変化は無いようです。
本書は、憲法改正について一人ひとりが自分で考えて判断するために、知っておくべき前提事実、様々な考え方をわかりやすく、丁寧に説明してくれています。憲法が改正された場合に一番影響を受ける若者(高校生42人)に向けた憲法の特別授業をまとめたもので、2019年に単行本として出版されたものが大きな反響を呼び文庫化されました。
まず「そもそも憲法とは何なのか」というところから、天皇制や基本的人権などについて身近な問題を切り口にその本質をわかりやすく解説しています。
特に本書が素晴らしいのは第4章以降にあります。憲法が成立した経緯から、だれがどのような思惑で押し付け憲法論や憲法改正を言い始めたのか、日米安保、高度経済成長期、55年体制の崩壊、そして今につながる改憲の流れをすっと理解できるように語っているので、憲法改正がよく分かり面白いです。
いま、憲法改正をめぐって様々な主張がなされています。自民党は(1)自衛隊の明記(2)緊急事態条項(3)合区解消・地方公共団体(4)教育充実の4項目。維新の会は(1)教育無償化(2)道州制導入などの統治機構改革(3)憲法裁判所の設置に加え、新型コロナウイルスの感染拡大から(4)緊急事態条項創設など。国民民主党はデジタル時代に即した人権保障のアップデートや統治機構改革を軸とする改憲などです。課題の解決に憲法改正が必要でないものも多く議論されています。本書は2018年に行われた授業なので、最新の議論について直接詳しい解説はしていませんが、憲法の本質から憲法にしかできないことは何か。憲法を変える前に基本法の改正で対応できることがたくさんあること。法律でできることは法律でした方が良い理由なども解説されています。
第5章では、集団的自衛権をめぐる解釈が大きく変更されたことが解説されています。本書はさらに踏み込んで、解釈の変更によって日本が核兵器を持つことや徴兵制を導入することも可能であることが指摘されています。
岸信介内閣の時に、「核兵器も必要最小限の実力として自衛のために使えるものであれば持つことは可能だ」という答弁があり、その後この方針が明確に否定されていないこと。非核三原則は国会で決議されているだけで法律でもないので、解釈によって集団的自衛権を認容した方法を用いれば、日本が核兵器を持つことも可能だということです。
徴兵制について歴代の内閣は導入を否定してきましたが、その根拠は、いかなる人も「奴隷的拘束も受けない」「意に反する苦役に服させられない」という憲法18条です。これも徴兵制が「奴隷的拘束」ではない、「意に反する苦役ではない」という解釈をすれば、変更される可能性はあるということです。
徴兵制についてはさらに、現代の兵器事情から徴兵制が役に立つのは白兵戦で敵同士が武器を持って戦うというような状況の時だといわれていることや、相手を攻撃するときは守る側の3倍の兵力がないと勝てないという「攻撃3倍の法則」を紹介し、日本の地理的条件などから近隣諸国が日本に攻め入る可能性などについても解説しています。
論争のあるテーマについて一定の見解を一切押し付けることなく、これほど深く、本質をわかりやすく解説する書はなかなかないのではないでしょうか。まだ読んでいない方がいたら是非、手に取ってほしい一冊です。
目次
はじめに
第一章 憲法って何?
君たちはどう考えるか?/自分で判断するために/立憲主義とは何か/憲法と法律の関係は?/教科書代は、なぜタダか?/憲法の条文は暮らしに関係する/働く上で知っておかなければいけない憲法と法律/憲法が定める三つの義務の意味は?/「裏口入学」で憲法改正⁉/「忖度」を生み出す政治/「主権者」である国民がどう考えるか/憲法に埋め込まれている三権分立/なぜ公文書を残すことが大切か/民主主義を支える「表現の自由」/自由と権利を守るためには/コラム【公文書】
第二章 天皇とはどんな存在?
大日本帝国憲法にも立憲主義が/「日本国民統合の象徴」とは?/自分の意思を簡単には表明できない立場/生前退位はどうやって決められたか/日本の国家元首は誰なのか/多大な力を持っていた大日本帝国憲法下での天皇/今後の天皇・皇室はどうなっていくのか/コラム【大日本帝国憲法がプロイセン憲法を手本にした経緯】
第三章 「最低限度の生活」とはどんな生活?
いまの憲法はどうやって生まれたか/戦争が終わり日本に求められたもの/日本国憲法の誕生/大日本帝国憲法への反省/基本的人権を守るために/日常生活に根を下ろしている憲法の存在/信教の自由と政教分離/学問の自由と信教の自由と公の支配/逮捕にも人権を意識/自由や権利を守るために/コラム【死刑存置国と廃止国】
第四章 憲法改正って何をどう変えるの?
憲法を変えるべきか、変えないでいいのか/日本国憲法は押しつけられたもの⁉/憲法改正論の源/憲法改正が争点にならなくなった戦後日本/変化する社会と世界情勢の中で/改憲へと今後進んでいくのか/具体的に憲法の何をどう変える必要がある?/LGBTの結婚は憲法問題/改憲勢力の本音/国のかたちを示す憲法/解釈次第で諸刃の剣にもなる憲法/憲法を知り、憲法を使う/コラム【LGBTとは】【世界で広がる同性婚】
第五章 もし国に「戦争に行け」と言われたら?
第九条を変えるとは?/集団的自衛権行使容認の背景にアメリカの影/個別的自衛権と集団的自衛権/これまで日本は集団的自衛権を認めてこなかった/変化してきた第九条の解釈/「いまの憲法のままでも日本は核を持てる」/徴兵制は必要?/日本は集団的自衛権で具体的に何をするのか/自衛隊をどう捉えればよいのか/憲法に自衛隊を書き込むと/第九条の改憲案もさまざまある/改憲の意味を考えるために/コラム【PKOと自衛隊の海外派遣】【非核三原則】
おわりに
主要参考文献
資料<日本国憲法全文>
【書籍情報】2022年1月、集英社文庫。著者は池上彰(ジャーナリスト)。定価は693円(本体価格630円)。
